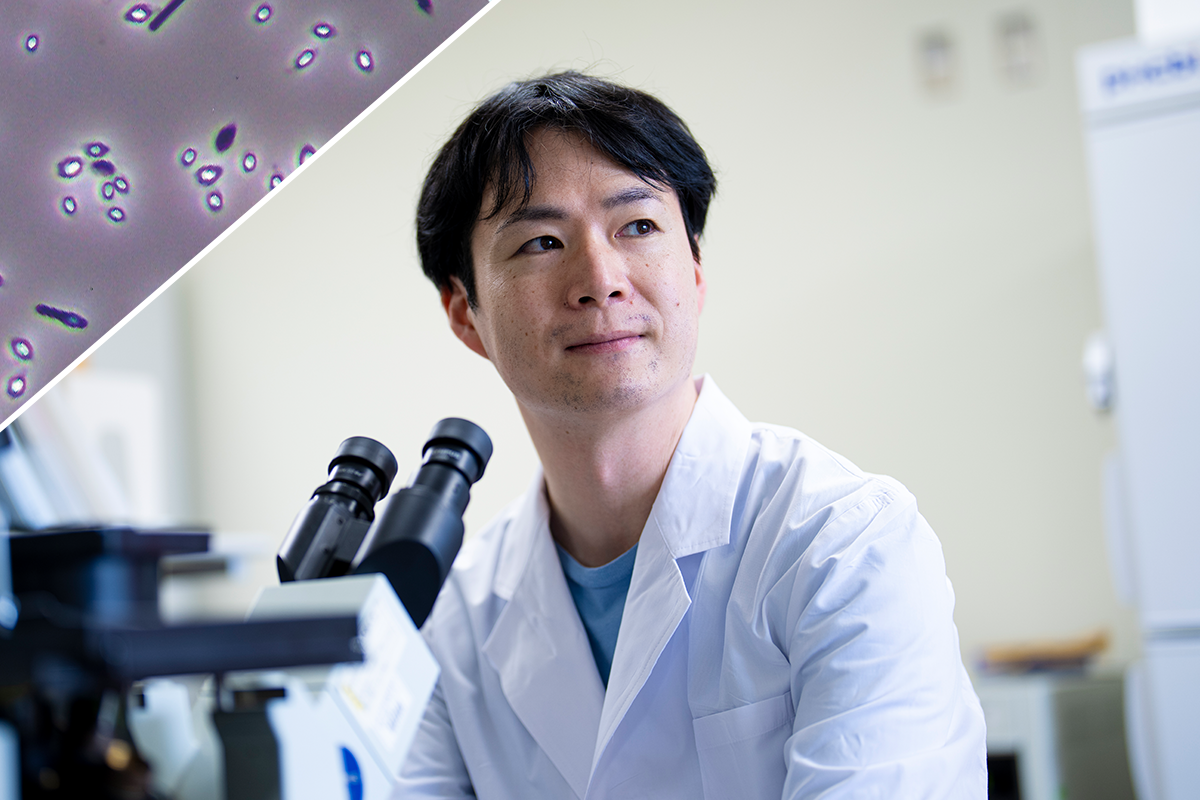研究内容
約半世紀、未解明だったポツリヌス菌の謎に迫る
1976年に米国で初めて発見されて以来、詳細な発症メカニズムが未解明な乳児ボツリヌス症。もしここで自分が挫折すれば、数年単位で研究が遅れてしまう。そんな強い覚悟を持ち、難解なテーマに挑み、社会実装を目指す――。そこまで突き動かすものは何か。
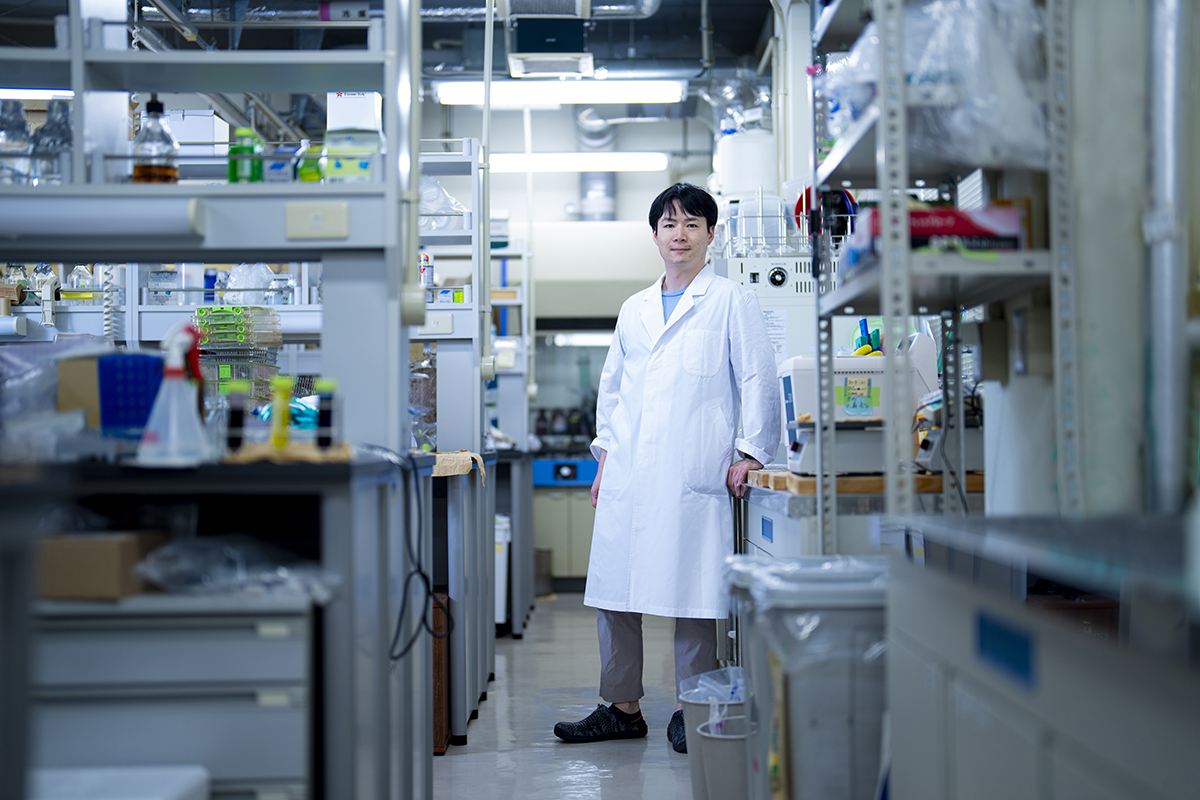
まわり道が教えてくれた
1歳未満の乳児にハチミツを与えてはいけない、と健診などで指導されます。これは、ハチミツがボツリヌス菌を含む可能性がある食べ物だから。ボツリヌス菌は強力な毒素をつくり、生後1歳未満の乳児に感染すると致死的な麻痺を引き起こします。ところが、健常な大人は基本的に感染しない。この「乳児のみが感染する」という特異な現象が探究心をくすぐり、どんどんのめり込んでいっています。
自然豊かな環境で生まれ育ち、生き物が好きな子供でした。高校生のとき授業で、生命現象を分子レベルで解明する分子生物学を知ると、その魅力に引き込まれていきました。高校卒業後は、生物学を学びたいと東北大学理学部に進学。学部生のときに免疫学、修士課程では細胞内輸送のメカニズムを研究する研究室に所属しました。入学時には博士号取得を宣言するほど意気込んでいたものの、いざ研究に関わると「自分はアカデミアで成功できるのか」と不安になり、悩んだ末に修士課程修了後は就職という進路を選択しました。
公務員として3年間、福島県農業総合センターで勤務。稲の品種開発や震災直後だったため土壌の放射能検査などを行っていました。安定した職業で、復興関連の業務はやりがいを感じていましたが、その一方で、博士課程に進んだ同期が苦労しながらも研究に励む姿を見て、「やっぱり、アカデミアで研究がしたい」。自分の心の内を確認することができました。

高まる興味と、社会的責務
よりアカデミックな研究者を目指し、慶應義塾大学の博士課程に進学。研究室は、腸管免疫・腸内細菌学の気鋭の研究者である長谷耕二先生のもとへ。厳しくもエキサイティングな環境の中で、自分より優秀な年下の後輩たちの姿に自信を失うこともありましたが、「一度大学を離れ、気持ちを固めたことがバネになっていた」と感じています。公務員時代の貯金は学費で全て使い果たしました(笑)。2019年に金沢大学に着任し、2年目から乳児ボツリヌス症の研究に従事しています。
1980年代初頭にアメリカのグループが、大人の持つ感染耐性には腸内細菌叢が関係すると報告して以来、詳細なメカニズムは未解明のまま。約40年間、ほぼ誰も手をつけていないテーマで、本当に手探りですが、どんな結果が出ても新しく、謎が謎を呼んで面白い。腸内細菌研究に必須の無菌マウスを用いた実験には、多額の費用が必要で、日本医療研究開発機構(AMED)から2度にわたり研究開発支援に採択されました。社会的関心の高さと、医学的に重要な研究に携わる責務をひしひしと感じ、基礎研究で得た知見を予防法や治療法の開発につなげ、社会実装まで目指したいです。
理学部出身の私にとって、「なぜだろう」と気になったことを突き詰めるところが研究の原点。現在はボツリヌス菌という特定の病原体について研究していますが、将来的には「なぜ乳児と大人で腸内細菌叢が異なるのか」「病原性細菌と共生細菌(※)は何が異なるのか」といったより普遍的なテーマに発展していく。各論から一般論を導き出すポテンシャルがあると感じています。
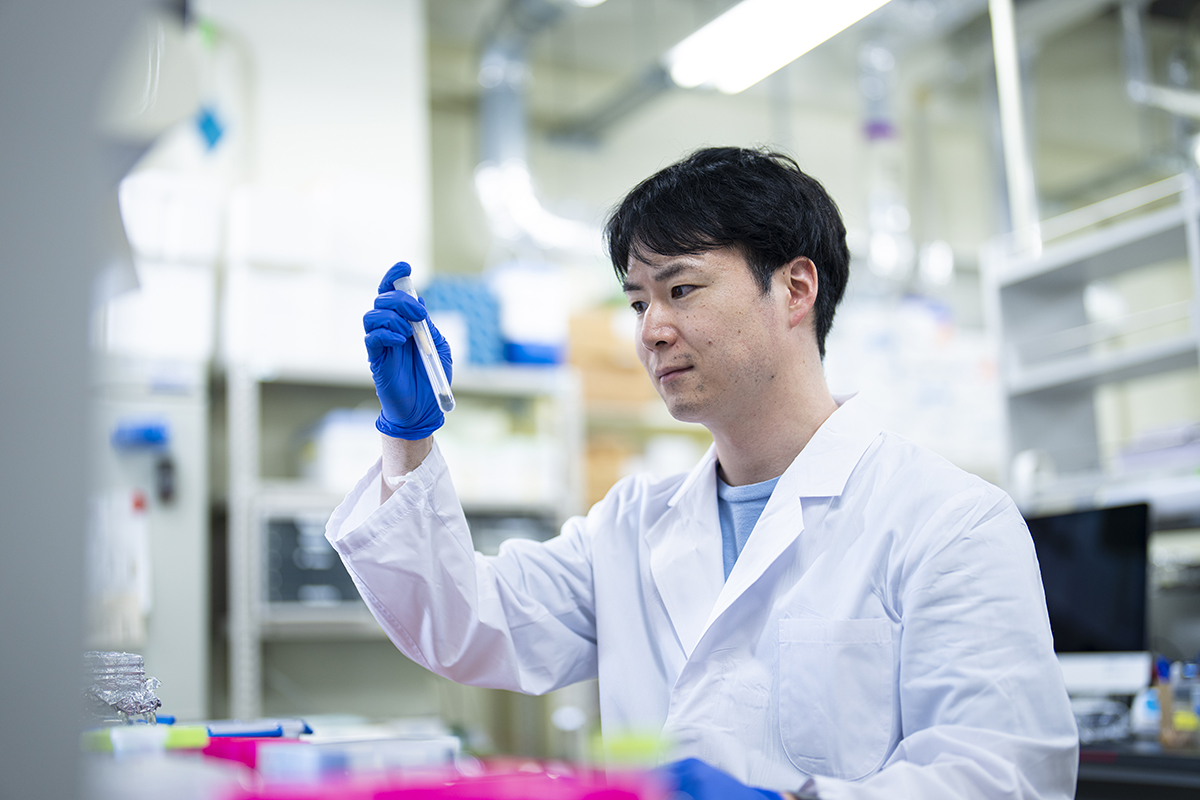
※人の腸や皮膚には多くの細菌が存在し、人類と共生しながら進化してきた。それらを共生細菌と呼ぶ。病原性細菌は毒素の産生など人に病気を引き起こす特殊な機能(病原性)を持つ細菌。