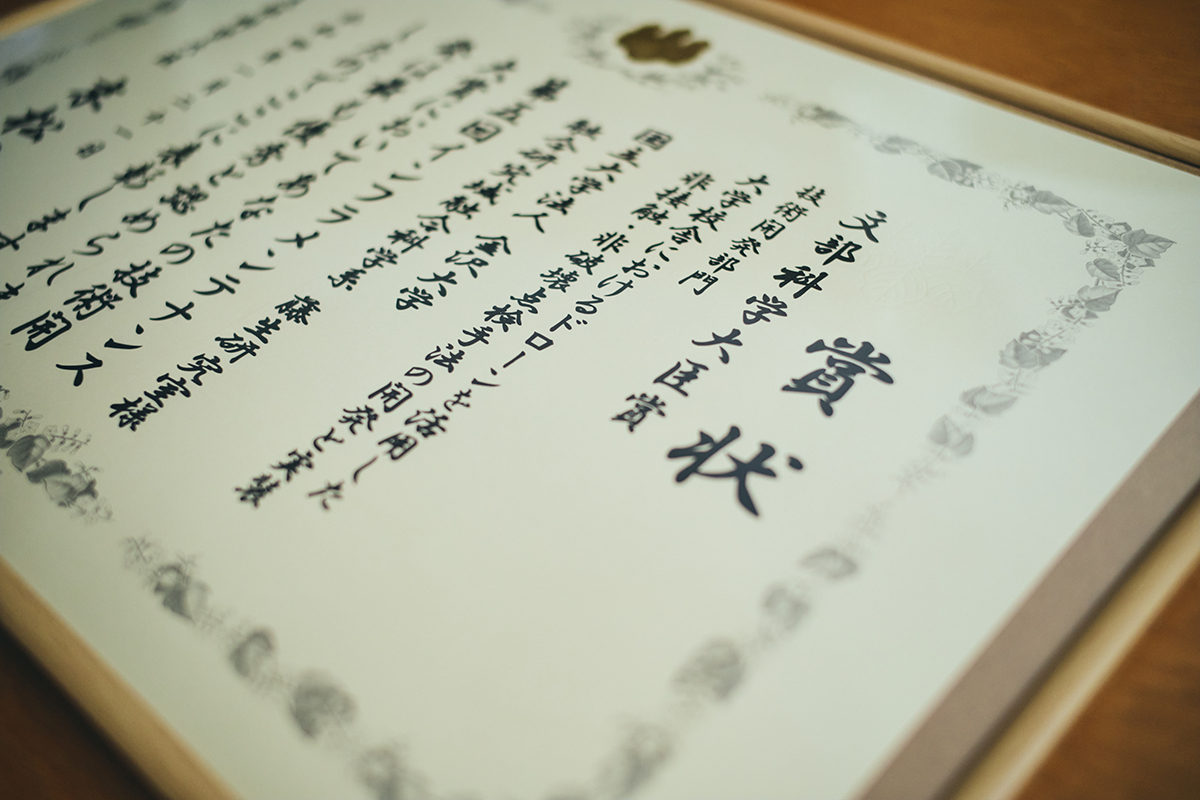研究内容
ビッグデータやAIを用いて、インフラ維持管理、交通、観光、防災などの都市課題を解決。
土木工学が専門の藤生慎准教授。土木というと道路工事やダム工事のイメージがありますが、カバーする領域は想像以上に広く、学際的です。ビッグデータやAI、ドローンなど最先端の技術を駆使し、安全で快適な生活基盤をつくるための実践的な研究を手掛けるのが、藤生准教授の流儀です。
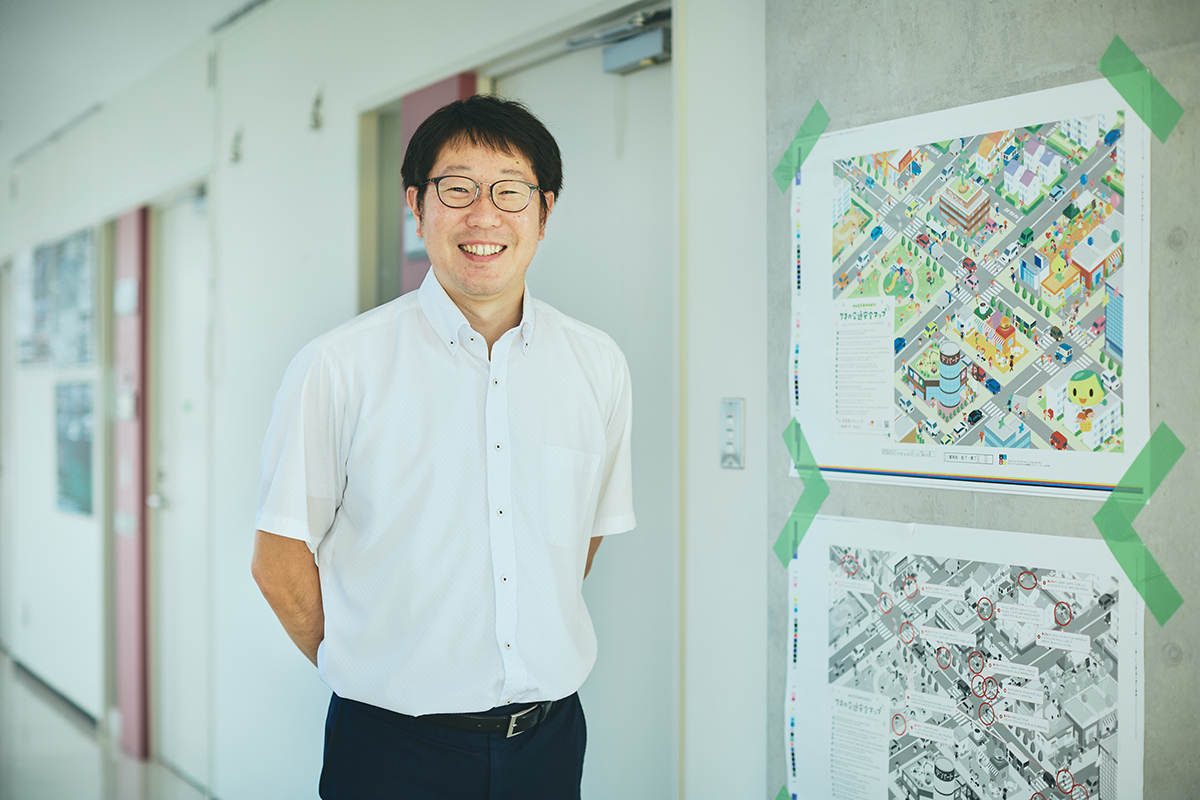
「論文を書いて終わり」じゃない
私は土木工学、中でも土木計画学を専門としています。原点は高校時代にあります。豪雨災害で自宅が床上浸水したことがきっかけで、被災後の復旧や、防災のためのまちづくりに興味を持つようになりました。
インフラの維持管理、交通、観光、防災と、現在の研究活動のすそ野は広いですが、根底に共通してあるのは、人や世の中をハッピーにしたいという思いです。そのためには、研究がアカデミアで閉じてしまってはだめ。企業や自治体との“協働”を意識し、研究成果の社会実装に積極的に取り組んでいます。
インフラ維持管理 ~足りないところに、AIの手を借りる~
2012年12月、中央自動車道の笹子トンネルで天井板が崩落し9人が死亡する事故が起き、高度経済成長期に建築された道路・橋梁・トンネルなどの老朽化対策の重要性が浮き彫りになりました。しかし膨大な数に上るインフラの維持管理には、人材、財源、技術力の3つが不足しています。
この問題を解決するために、AIを使った点検技術を開発しています。超高解像度カメラで撮影した映像をAIで解析することで、0.2ミリ以下の微細なひび割れまで検出でき、最終的に人間の目でチェックを行って点検が完了します。炎天下や寒空に現場で足場を組む必要もなく、大幅な省力化が可能で、点検の品質の安定、効率化にもつながります。
交通、観光 ~人の流れを変える~
交通と観光の領域では、陸・海・空を対象に、人の流れを見つめています。特に北陸新幹線開業やクルーズ船の寄港で注目を集める金沢に焦点を当て、旅行者の観光行動や交通手段について継続して調査を実施しています。集めたビッグデータは、旅行客のニーズに応じたサービスの開発や、戦略的な観光施策の立案に役立てることができます。AIが観光スポットの混雑を予測し、最適な周遊ルートをリコメンドする技術の開発は、その一例です。北陸新幹線の金沢-敦賀延伸を経て、今後は北陸3県でビッグデータを活用した観光の取り組みを強化していく計画です。
交通については利便性だけでなく、安全性に着目した研究も行っています。「7才の交通安全プロジェクト」は、交通事故統計データを分析することから始め、地域の幼稚園の協力を得てさまざまな実験を行い、得られた知見を「交通安全マップ」に落とし込んでいます。

防災 ~能登の創造的復興を支える~
防災については、構造物の耐震化など事前の災害抑止力の強化、災害が起きた後を考える災害対応力の充実、そして復旧・復興戦略という、災害マネジメントサイクルの各フェーズで、長年の研究の蓄積があります。
金沢大学が立地する石川県では、2024年1月1日に能登半島地震が発生しました。私たちは翌2日から能登に入り、人工衛星データを使った被害の実態把握にいち早く着手しました。現在はドローンも活用し、宇宙と陸の両方から被災地をモニタリング。航空写真から家屋の損傷具合を判定するAI技術の開発をはじめ、さまざまな調査・研究・実践を通じて能登の創造的復興を支えています。
能登は他地域に先んじて過疎化・高齢化が進む、日本の課題先進地です。国内では近い将来、大規模地震の発生が懸念されており、能登の災害マネジメントサイクルや、創造的復興のプロセスから学ぶことは少なくありません。たとえば私たちは、以前から国民健康保険データベースを活用し、地域の健康状態を把握する研究に取り組んできましたが、これらのデータを活用すれば、地域で備蓄すべき医薬品の検討や、災害時の効率的な医薬品供給が可能になります。医薬品に限らず、まちづくり、観光、モビリティ、ウェルビーイングなどに関する膨大なデータの蓄積を活かし、AIを駆使して、能登の未来の姿を予測しようという大規模なプロジェクトも進行しています。